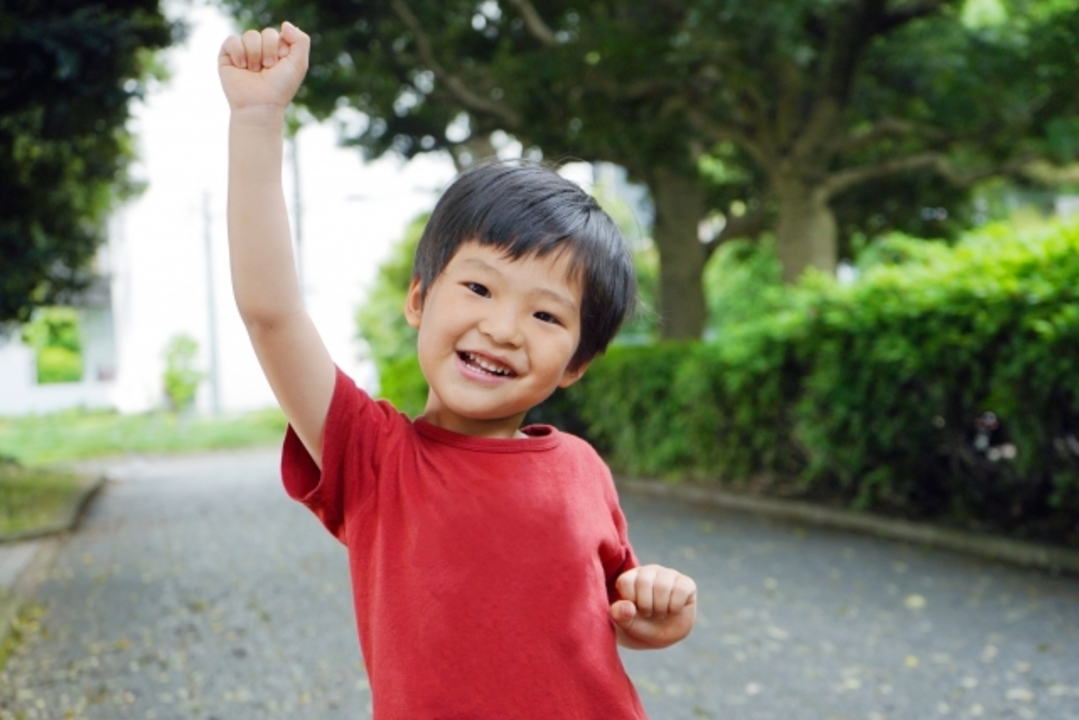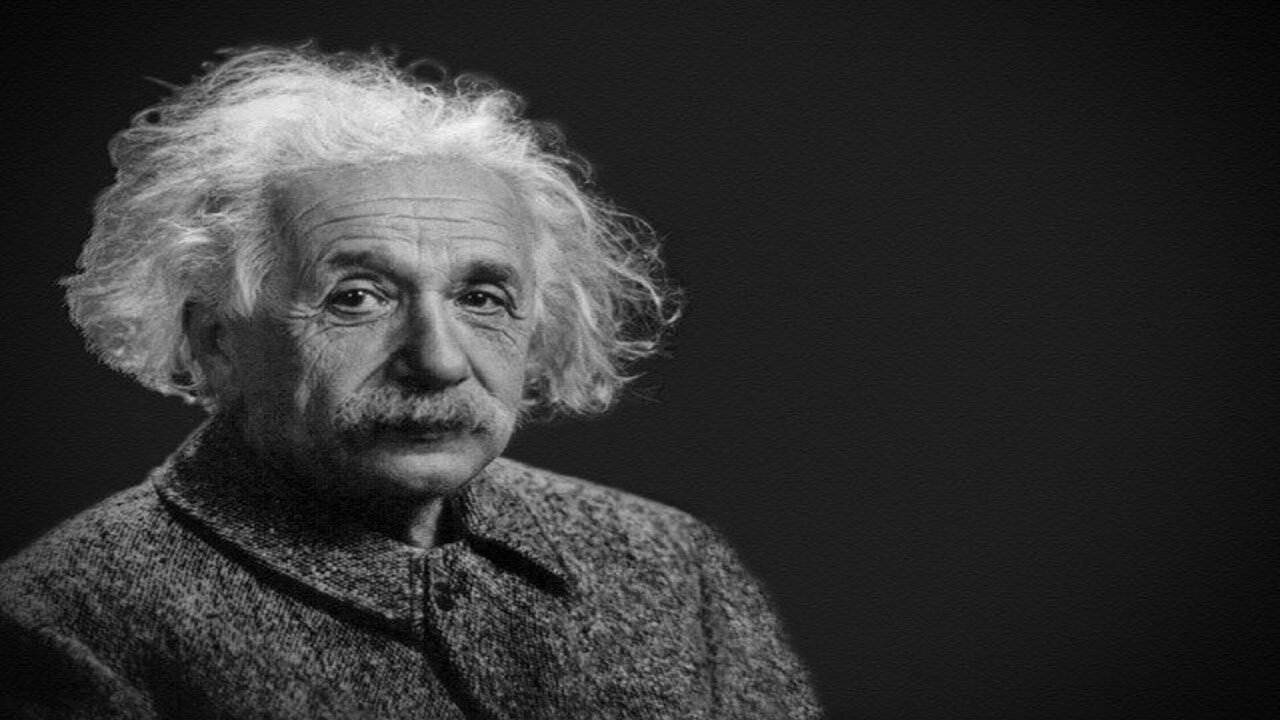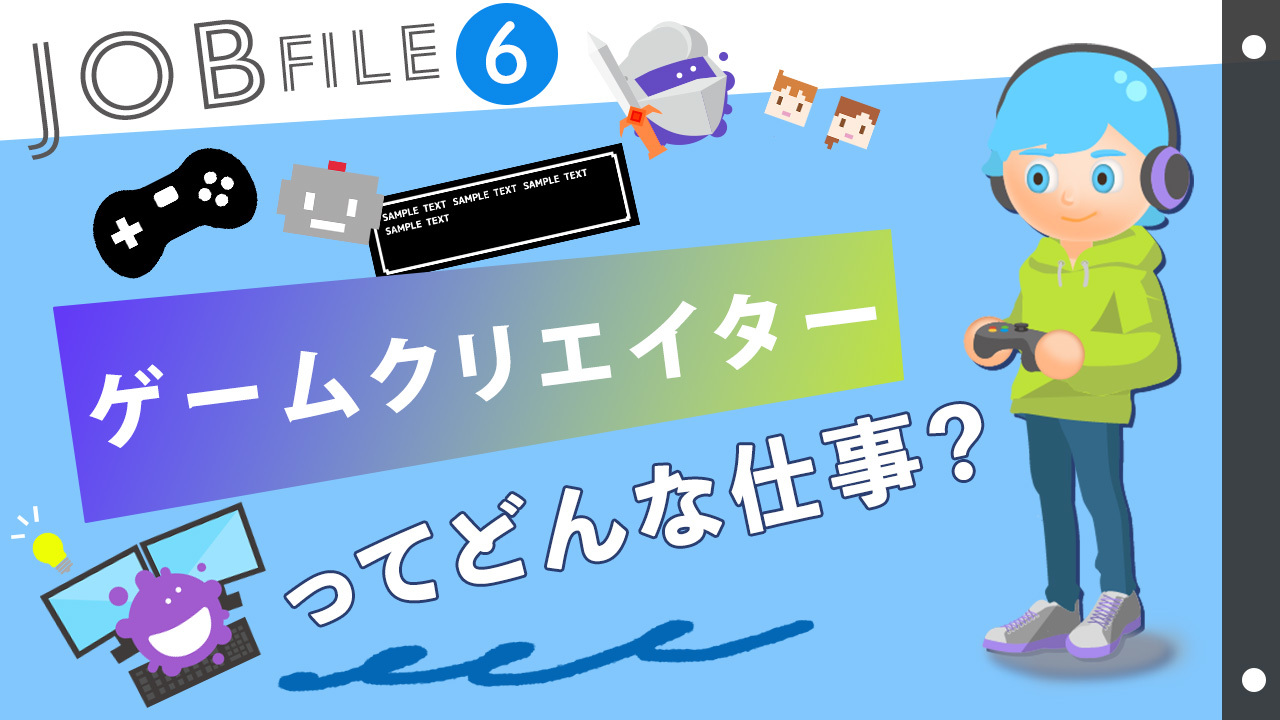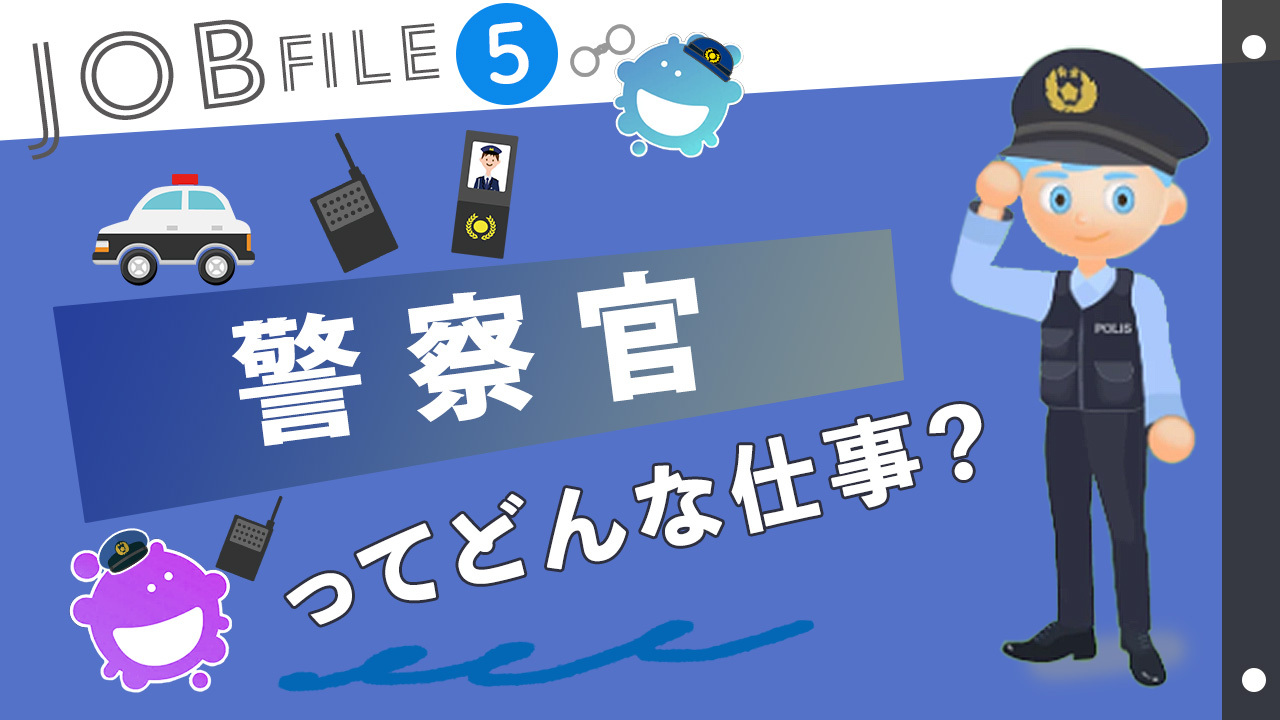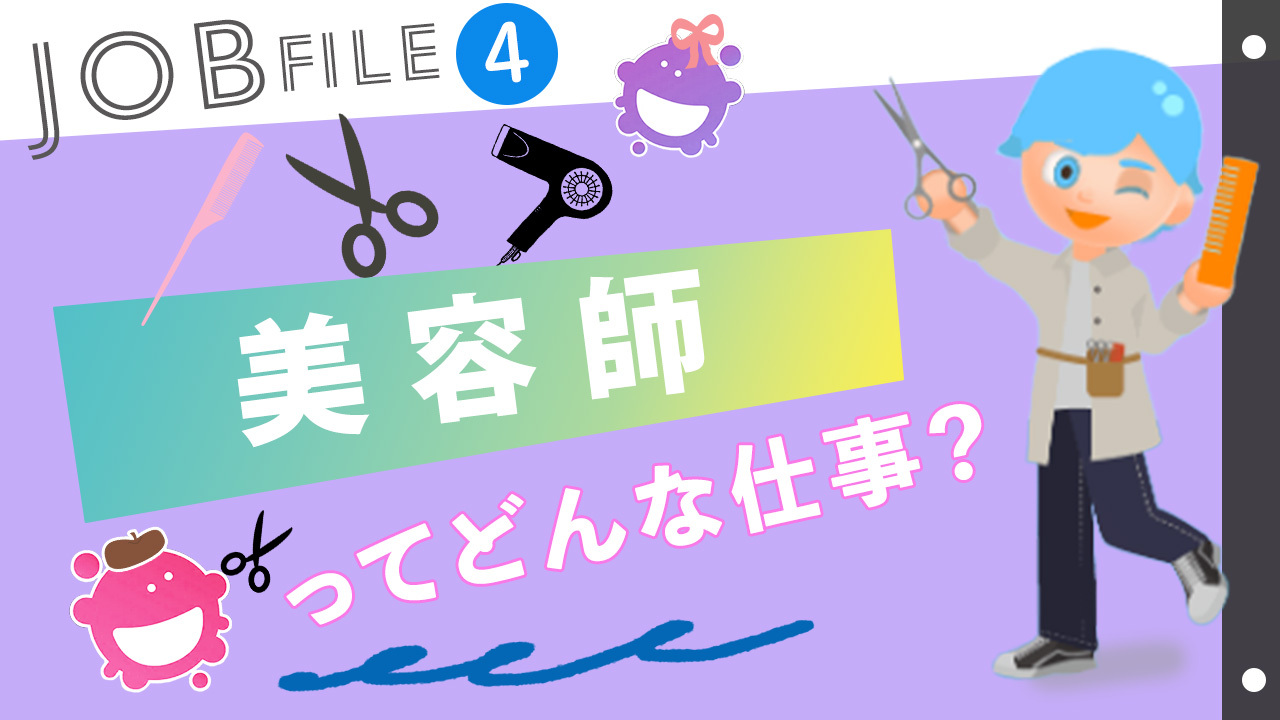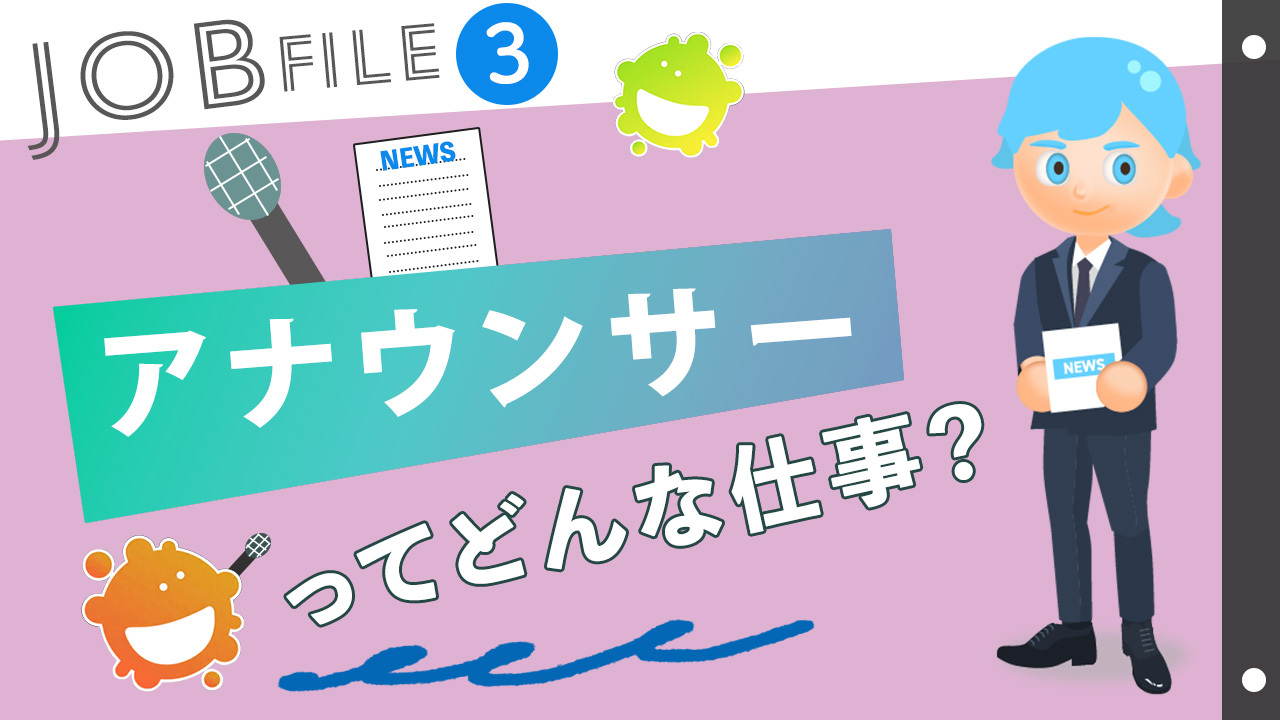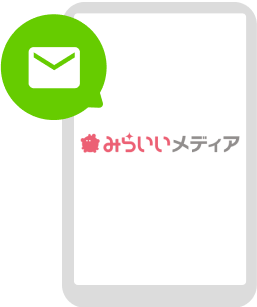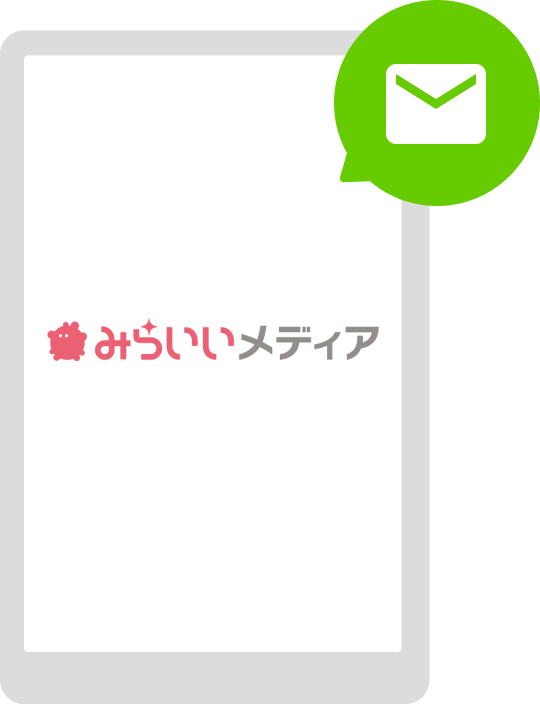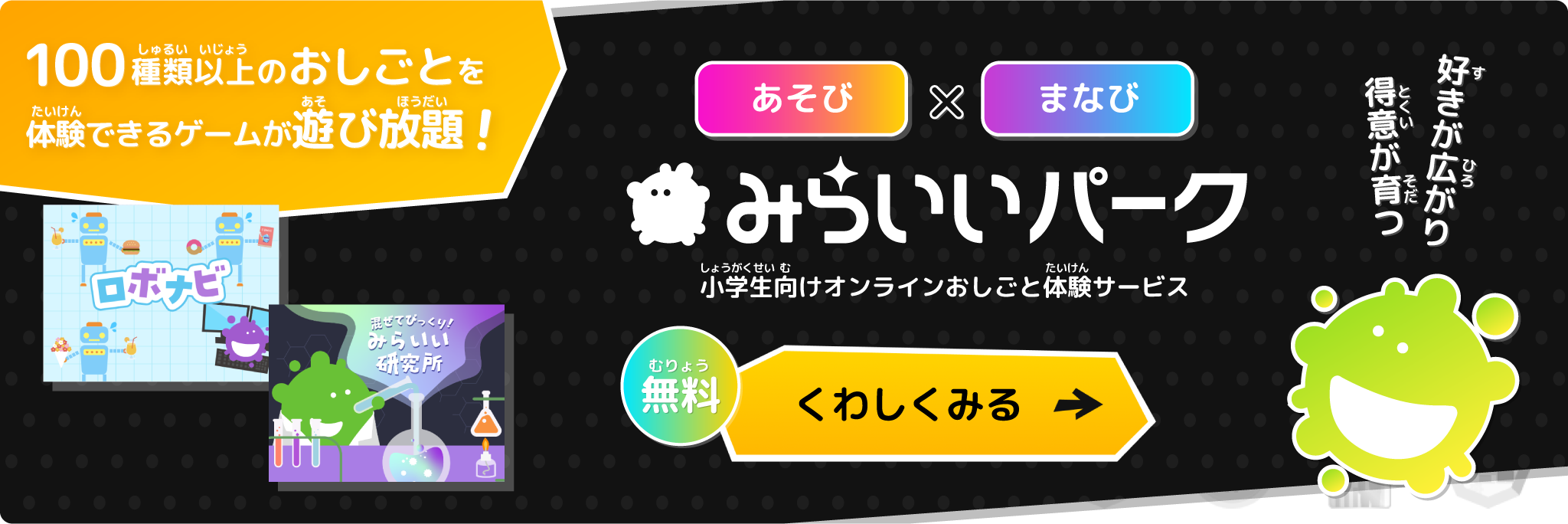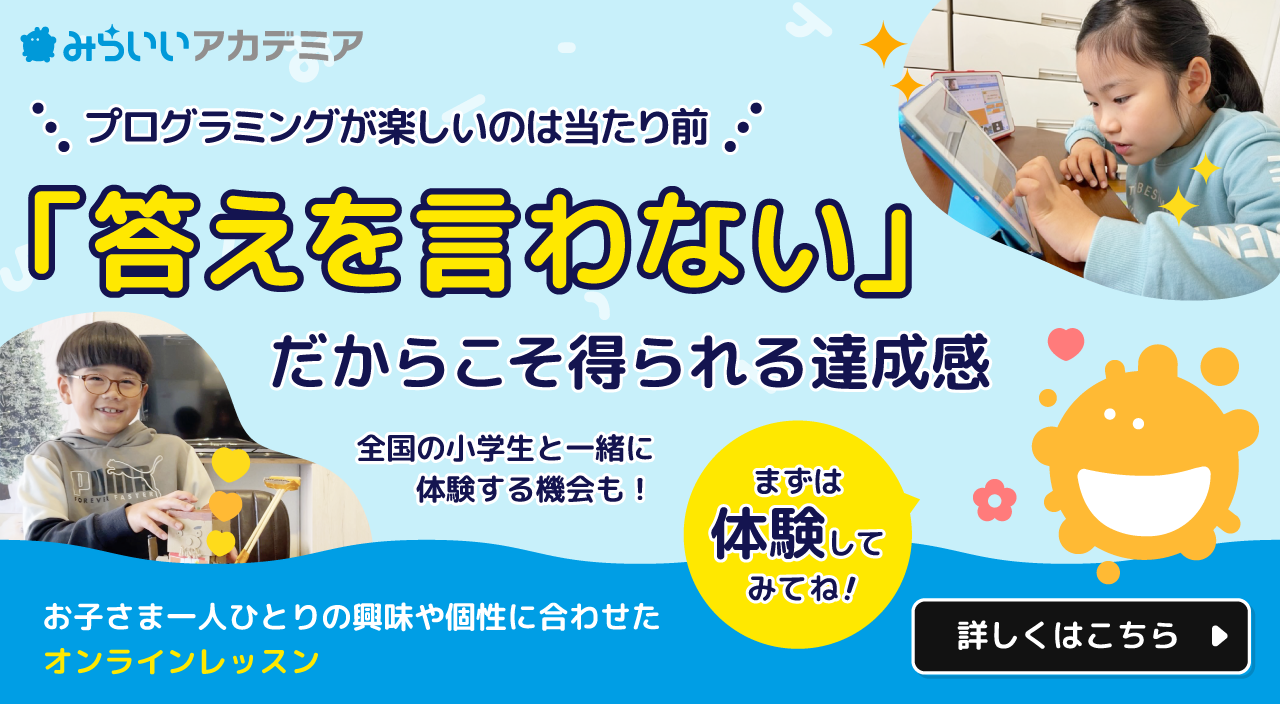海外のお小遣いはいくら?渡し方や取り入れたい考えも紹介!

海外ではお小遣いをどのくらい渡しているのでしょうか?今回は、海外のお小遣いを中心に、子どもに対するお金の教育のあり方や考え方をお伝えしていきます。家庭にも取り入れたい考え方もあるので、参考にしてみてください。
各国の平均月額お小遣い

まずは、各国の平均お小遣い金額をみていきましょう。こちらは、2020年にアクサ・インベストメント・マネージャーズが実施した調査をもとに作成しました。この調査は、800万円以上の年収のある所得層の上位80%が対象です。子どもの対象年齢は8〜15歳です。
.png?w=800&h=474)
参考:アクサ・インベストメント・マネージャーズ 2020年度投資家意識調査 日本の子ども、国際比較では“お金”について学ぶ機会少ない
表を見てみると、国によって金額にばらつきがあります。日本は台湾に次いで2番目にお小遣いが少なく、経済成長が著しい香港やシンガポールでは、月に1万円を超える金額になっています。
また、アメリカのお小遣いは、子供の年齢ごとに週に1〜2ドルを支払う場合が多いようです。そのため、10歳であれば、4200円〜8400円(2020年の米ドル対円相場を参考)程度になるようです。
一見金額だけみると、日本と海外ではかなりの差があるように感じられます。しかし、これには、お小遣いに対する考え方の違いが影響しているのです。続いては、海外と日本のお小遣いに対する考え方の違いを紹介していきます。
国によって異なるお小遣いに対する考え方

他の国にあるように、小中学生の子どもに毎月1万円のお小遣いは多いように感じられるかもしれません。その理由の一つには、日本では、お小遣いは自分の好きなものや遊びのために使うものだと考えられているからではないでしょうか。
日本のお小遣いへの考え方
学研教育総合研究所が2020年に、小学生のお小遣いの使い道を調査しました。その調査で使い道の1位は「お菓子などの食べ物」(49.2%)、2位が「貯金」(42.6%)、 3位が「おもちゃ」(31.2%)でした。この調査からわかるように、日本の子どもたちは自分の好きなものを買うことが多いようです。このような経験があるからこそ、お小遣いを渡すようになった大人も、好きなものに使いなさいという感覚でお小遣いを渡すことが多いと考えられます。
また、お小遣いを定額制で渡している場合、月に1万円は高いと感じられるかもしれません。お小遣いへの考え方と、お小遣いの渡し方を中心に海外のお小遣い事情をみていきましょう。
欧米のお小遣いの考え方
欧米では、 お小遣いは、子供たちが金銭感覚を学び、責任感を養うためのツールとして捉えられています。お小遣いの渡し方は、家事のお手伝いや目標達成などに応じて与え、自分で計画的に使うことを教育します。
例えば、アメリカのお小遣いの金額が高いのは、日用品も自分自身で購入するからです。文房具を始め、洋服やバッグなど自分が必要なものはお小遣いの中から購入しています。労働の対価としてお小遣いを渡す場合が多く、芝刈りや隣の家の犬の散歩など自ら仕事を探して、仕事に取り組んで稼ぐことも経験するそうです。イギリスでもノージョブノーマネーという考え方が一般的で、家事手伝いの対価などでお小遣いをもらうようです。
治安の観点から、子どもに現金を渡さない国もあります。現金を持っていると盗まれる危険性があるという考えがあるからです。そういった国ではキャッシュレス文化が進み、デビットカードが渡されることもあるようです。自分のお小遣いで、小学生でも好きなように買い物ができるのは、日本のいいところといえますね。
アジアのお小遣いの考え方
アジアのお小遣いは、子供たちへのご褒美や、ちょっとした楽しみとして捉えられている傾向があります。自分のものに使うというイメージは日本の使い方と似ていますね。一方で、お金を自由に使わせて自主性を育むことを目的としているようです。大人からすると、一見無駄遣いのように思えるかもしれない買い物も、子どもにとっては意味のある買い物かもしれません。つい「またそんなものを買って」と口出しする前に、なぜそれを買ったのか、買った理由や、買ったときの子どもの気持ちなどを聞いてあげましょう。
また、高橋登氏らが編集した、日本、韓国、中国、ベトナムのお小遣い文化の違いをまとめた『子どもとお金』によると、人との交流のためにお金を使いなさいと教えられるようです。友達同士で遊んでいて、お菓子が買えない子がいたら、その子の分も買ってあげなさいということです。自分のことは自分でやる、人に迷惑をかけてはいけないという考え方が強い日本からすると新鮮な考え方ではないでしょうか。お金の大切さや、お金は使うことで力を発揮するというお金の性質などを理解できたら、自分が困らない範囲で、人にお金を使うことも検討してみてもいいかもしれません。
【参考文献】高橋 登、山本 登志哉『子どもとお金』,東京大学出版会,2016
日本のお小遣い制度で多い「定額制」の特徴3つ

続いては、日本のお小遣い制度で多い定額制の特徴を3つ紹介します。海外では、働いた分だけお小遣いを渡すのが一般的でした。日本でも、取り入れている家庭はあるかもしれません。しかし、まだ定額制の家庭もまだまだ多いと思います。改めて、定額制の特徴を3つ紹介します。
- 予算内でやりくりする力が身につく
- 保護者とお金の使い道の振り返りができる
- ありがとうの対価としてお金をもらうという感覚が身に付きづらい
予算内でやりくりする力が身につく
お小遣いを定額にすることで、予算内でやりくりする力が身につきます。定額制にすると、毎月もらえる金額には上限があるため、限りあるものの中で満足できるように工夫していく力を伸ばせます。また、衝動買いを減らせたり、必要なものを買えるようになったり自分の欲との付き合い方も学べるのです。
保護者とお金の使い道の振り返りができる
定額制は、毎月一定額もらえるからこそ、あまり考えずに無駄遣いをしてしまうことも多いです。そのため、お金の使い方や振り返りが大切です。お小遣いが定額だと、保護者は子どものお小遣いの使い道を把握しやすくなります。保護者がお小遣いの金額を把握できているからこそ、使いすぎではないのか、お小遣いに対して大きな金額ではないのかを一緒に考えることができます。また、お金の使い道の振り返りもしやすくなります。
ありがとうの対価としてお金をもらう感覚が身に付きづらい
毎月一定額お金がもらえると、自分で稼いだという感覚が身につきづらいのも特徴の一つです。何もしなくてもお金がもらえるという考えでは、将来苦労してしまうかもしれません。お金はありがとうの対価であることが伝えられるといいですね。いきなり全額をお手伝いの対価とすると、子どもたちもお手伝いをする気持ちにはならないかもしれません。稼ぐという感覚を身につけてもらうために、半分は稼いでもらう、何か成果をあげるために頑張った対価として渡すなど、渡すだけでない工夫ができると良いですね。
取り入れたい海外のお小遣いへの考え方

お小遣いをただ渡すのではなく、子どもの力を伸ばすツールにしてみるのもいいかもしれません。子どもの成長につながる、取り入れたい海外のお小遣いへの考え方を紹介します。
- プレゼンをさせてみる
- 人の役に立つとありがとうの対価としてお金を受け取ることができる
- 「必要」と「欲しい」の貯金箱を作る
プレゼンをさせてみる
海外では、自分のお小遣いで買えないものは、子どもたちが保護者にプレゼンをすることがあるようです。なぜそれが欲しいのかという子どもの気持ちの部分や、手に入れることのメリットやデメリットと対策、欲しいものの金額や送料はいくらかというお金のこともを調べてプレゼンをするそうです。
プレゼンをするためには、商品について調べる必要があります。商品について調べると、お金についても適正金額を知ることができ、本当に新品で買う必要があるのかなども考えることができます。メリットやデメリットは、初めは子ども自身に関するものだけでよいですが、慣れてくれば、両親や家族、友達など少しずつ範囲を広げていくと、社会に出たときにも使える考え方になります。自分の考えを根拠を持って伝える経験ができるので、欲しいものがあると言われた時にはプレゼンをしてもらうように提案してみてはいかがでしょうか?
人の役に立つとありがとうの対価としてお金を受け取ることができる
海外のお小遣いでは一般的で、日本でも少しずつ取り入れられている稼ぐ方法を取り入れてみるのもいいですね。お皿洗いや掃除をしたらいくらというルールで初めてもよいのですが、他にも、保護者に頼まれる前にやったらプラスで金額がもらえる、手作りのものを販売する、不用品を売るという方法もあります。
頼まれる前に取り組んだらプラスの料金がもらえるという方法は、一見稼ぐことに繋がらないかもしれません。しかし、この方法にすると、子どもたちは頼まれそうなことは何かを観察したり考えたりする必要が出てきます。そして、それを実行して報告する必要もあります。これは、人のためになることを探す練習になります。お金はありがとうの対価ですので、まさにありがとう探しから、ありがとうを得るまでを体験することができるのです。
こちらの記事では、子どもの稼ぐ力を伸ばす方法について解説しています。
小学生からお金を稼ぐ感覚を身につけよう!おうちアルバイトの方法とは?
「必要」と「欲しい」の貯金箱を作る
お小遣いの管理方法の工夫もできそうです。海外では、お金を管理する力を身につけさせるために、多めの金額を渡しているとのことでした。お金を管理するには、「必要」なものと「欲しい」ものを分けて考える必要があります。言葉で理解していても、それを買い物の時に実行するのは難しいものです。その練習をするために貯金箱を分けておくのです。
欲しいものができた時には、すぐに購入するのではなく、どちらの貯金箱から使うかを考えるのです。時間を置くことで、冷静に考えることができ、2つのうちどちらなのかを考える習慣も身につけられます。
お小遣いを活かして子どものお金に関する力を伸ばそう!
海外では、小さいうちからお金に関する力を伸ばすために、自分で管理をさせるという考え方が一般的でした。お小遣いをただ渡して終わりのものにするのではなく、子どもの能力を伸ばすツールという考え方には新たな気づきもあったのではないでしょうか。日本の定額制にもメリットはあるため、海外での方法とも組み合わせてみてくださいね。
こちらではお小遣いを通して学べることをより詳しくお伝えしています。
【いま注目!】子どものお小遣いを管理する時に知っておく3つのこと!
海外と日本の問題を紹介した記事はこちらです。
生きる力がないとは? 〜自分自身に満足できない若者が多い日本〜